MQLとは?SQLとの違いにも触れつつ詳しく解説!
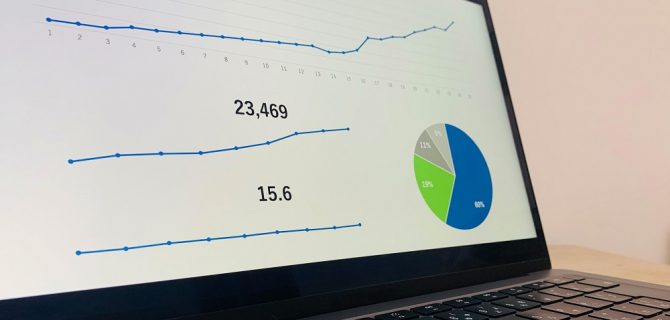
企業活動においては、見込み顧客の購買意欲を高めるための仕組みづくり、すなわち「リードマーケティング」が欠かせません。そのプロセスのなかで、見込み顧客を段階的に区分したとき「MQL・SQL」と呼ばれる層がいます。今回はMQLやSQLの概要、マーケティングにおける両者へのアプローチ方法について解説します。
目次
MQLとは
見込み顧客のなかでも、とくに商品への関心が高い場合をMQL(Marketing Qualified Lead)といいます。MQLはホットリードと呼ばれることもあり、的確かつ効率的なマーケティング活動を行ううえで重要な概念です。
マーケティング施策を通じて興味を持った見込み顧客は、総じてリードと呼ばれます。しかしリード全体をみると購買意欲には差があるため、それぞれ段階的にアプローチ方法を変える必要があるのです。なかでも購買意欲の高いリードをMQLとすることで、アプローチすべきターゲットを絞ることが可能になります。
SQLとは
マーケティング活動による見込み顧客の初期段階がリード、その次がMQLとすると、さらにその先にあるのがSQLです。SQL(Sales Qualified Lead)とは、営業部門の活動を通して生まれた、最も自社商品を購入する可能性の高いリードを指します。MQLと比べると、よりニーズや購入時期などが明確かつ具体的に決まっているのが特徴です。
MQLとSQLの違い
MQLとSQLは、どちらも購買意欲の高いリードであるという共通点があります。しかし、それぞれ主導する部門に大きな違いがあります。
MQLはマーケティング部門の戦略により創出されたリードです。その情報は営業部門へと引き継がれ、SAL(Sales Accepted Lead)と呼ばれます。そして、SALをはじめとした営業部門が担当するリードのうち、購買意欲が極めて高いと判断されたリードがSQLとなるのです。最終的には、SQLに向けた商談・ヒアリングなど重点的なフォローを行うことで、受注・契約獲得を目指します。
MQLとSQLはそれぞれマーケティング・営業と担当部門が異なりますが、BtoBマーケティングにおける一連のプロセスの中で、つながっているといえるでしょう。
MQLの特徴

リードのなかでも、購買意欲の高いMQLは重要なターゲットです。では、MQLを特定することで、マーケティング戦略においてどのようなメリットが生まれるのでしょうか。ここでは3つの特徴について解説します。
営業活動を効率化できる
MQLを把握していれば、ターゲットをある程度絞った状態からアプローチできるため、営業活動の効率化が見込めます。またMQLは通常のリードに比べて購買意欲が高く、自身のニーズもある程度決まっています。そのため、フォロー体制次第では成約につながる可能性が高いというメリットもあるといえるでしょう。
改善点が見えやすい
MQLがもつ高い購買意欲の背景には、企業への強い関心・信頼があります。そのためサービス向上に向けた改善点や疑問点などのフィードバックを、真摯に伝えてくれる場合が多いです。そこから企業の課題が客観視できるため、今後の運営にいかすこともできるでしょう。
リピーターを獲得できる
自社商品に対する関心が高いMQLは、購入後もリピーターになってくれる可能性があります。そのためには新たに顧客を増やすだけでなく、購入前後のアプローチ方法を工夫することが大切です。具体的には、営業活動の段階でMQLの課題や予算などを丁寧にヒアリングする・課題解決策を提案するなどが挙げられます。加えて、購入後のフォローも忘れずに行いましょう。
MQLを創出するには
ここまででMQLの重要性について説明しましたが、実際どのようにリードを獲得し、購買意欲向上にむけた育成を行えばよいのでしょうか。ここでは、そのプロセスを三段階に分けて説明します。
リードジェネレーション
まず行うのは、リード獲得を目的とした「リードジェネレーション」です。主な方法としてはオンライン・オフラインの2種類があり、具体的には以下の通りです。マーケティングの効率化を目指すなら、リード情報の管理が行えるMAツールなどの導入もおすすめです。
(1)オンラインでのアプローチ方法
- デジタル広告(メディアを通じた宣伝広告)
- オウンドメディアマーケティング(Webマガジンやブログなど)
- SNSマーケティング(SNSの投稿や発信によるアプローチ)
(2)オフラインでのアプローチ方法
- 展示会の開催(名刺交換など)
- セミナーの開催(自社へのイメージアップ、購買意欲向上)
- 電話でのアポイント獲得
- ダイレクトメール(FAXや郵送で、キャンペーン情報などを届ける)
しかし、これらの方法を単に実践するだけでは効果は見込めません。まずはどのようなリードを獲得したいのか、ターゲット層を明確にすることが大切です。
リードの獲得方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
リードナーチャリング
リード獲得後は、購買意欲向上にむけた「リードナーチャリング」を行います。リードジェネレーションの段階では、商品への興味はあっても購買意欲はそれほど高くない傾向にあります。そのため、メルマガ配信やWeb会員ページへの誘導などを行いながら、リードが商品を購入したいと思えるようなイメージの共有・定着を図ります。
ナーチャリングの方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
リードクオリフィケーション
リードナーチャリングが完了すると、リードの購買意欲は高まった状態になります。そこから、営業部門へと引き渡すリードを絞り込む「リードクオリフィケーション」に移ります。
絞り込むうえで大切なのは、マーケティング部門と営業部門でMQLの基準を設けることです。基準は各企業によって異なりますが、絞り込む方法としてはリードのアクティビティをスコア化して順位付けする「スコアリング」が一般的です。メルマガページのクリックや閲覧・Webへの問い合わせ回数などを分析し、スコアが高い場合は購買意欲の高いリード、すなわちMQLとして判断します。こちらもリードジェネレーションと同様に、MAツールを活用することで効率よく分析・管理できます。
MQLとSQLを連携させる方法
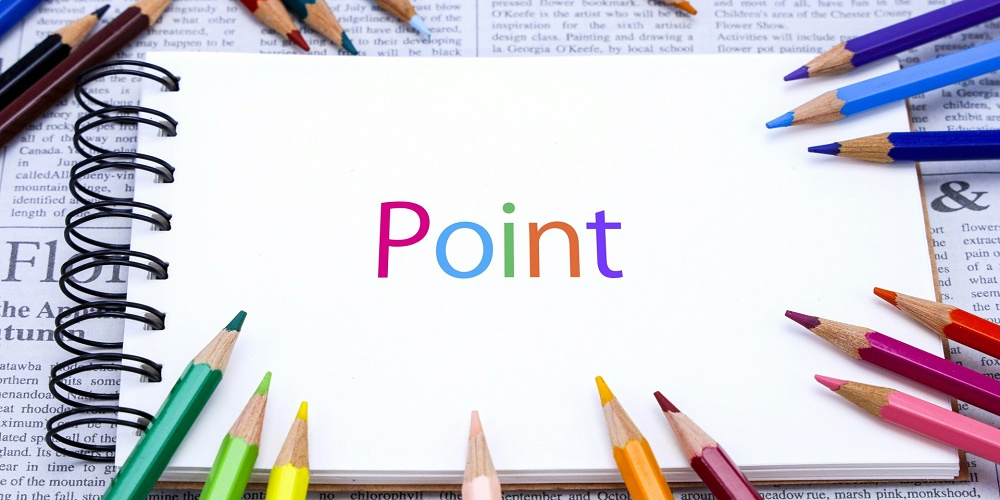
先述した3つのプロセスによりMQLを創出できれば、いよいよ営業活動を通じてSQLへと移行していきます。このとき重要なのは、マーケティング担当と営業担当で連携を図ることです。では具体的に、MQLをSQLへとつなげるためのポイントについて3点解説します。
部門間の情報共有を徹底する
MQLとSQLの連携トラブルが発生する理由の一つが、部門間における情報共有の不足です。これを防ぐためには、マーケティング部門が営業部門に対して、MQLに関する顧客情報を細かく伝えることが大切です。共有すべきおもな内容は以下の3点で、これらはスコアリングの際に基準として用いられることもあります。
- MQLの属性(企業・部署・役職・業種・地域など)
- リードやMQLとなるまでの経緯
- MQLに対して行ったリードナーチャリングの内容
役割分担を明確にする
先述したように、リードはそれぞれ属性や購買意欲の程度が大きく異なります。そのためリードを段階ごとに細かく分けて、各ステージに合ったアプローチ方法を行う必要があるのです。MQLやSQLを設定する理由もそこにあります。
そしてMQLをSQLへとスムーズに移行させるためには、段階ごとに必要なアプローチ方法をチーム全体が把握し、それらを各部門に振り分けることが大切です。たとえば、リード育成やニーズの調査をマーケティング部門が担当し、購買意欲の高いMQLを見極めます。そして、引き継いだMQLの情報をもとに営業部門が商談やクロージングを行えば、精度の高いSQLの創出につなげられます。
マーケティングの効率化を実現するには、細かな情報共有と役割分担を部門全体で行うことが重要となります。
商談ステージを設定する
MQLの定義により目指すゴールは「購買意欲の高いリードを厳選し、営業部門へとつなげる」ことです。これにより営業部門はMQLに対して重点的なアプローチができ、SQLの精度を高められます。ですが、まだリードを育成しきれていない段階で引き渡してしまうと、かえって営業部門からのアプローチがしづらくなります。これでは、リードを各段階で分ける意味がありません。
そこで大切なのは、リードクオリフィケーションの基準をマーケティング部門と営業部門で一緒に考案することです。双方が納得できるレベルでMQLが創出できてはじめて、MQLやSQLの定義による効果が発揮されるでしょう。
まとめ
この記事ではマーケティングにおけるMQLを創出するメリットと方法、SQLにつなげるためのポイントについて解説しました。MQLを定義することは、マーケティング活動をはじめ運営全体が効率化するうえで有効な手段です。一方で、部門間での情報共有や役割分担が必要であるなど注意すべき点も多くあります。今回の内容を踏まえて、リードに対する的確なアプローチや工夫ができているか、今一度確認してみるとよいでしょう。



